松岡 靖浩
Yasuhiro Matsuoka
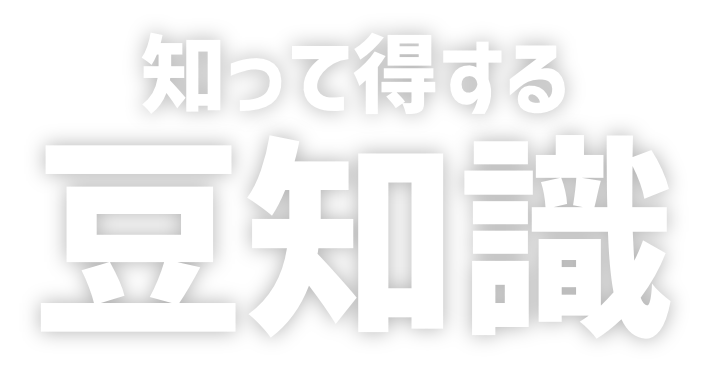
経営者として以下の算式はぜひ知っておいてほしいですね。
1. 粗利益率
売上-仕入=粗利益額
この粗利益額を売上高で割ったのが粗利益率になります。
例えば八百屋さん。りんご仕入れ600円、売上1000円。
粗利益額は1000円-600円=400円
粗利益率 400円/1000円=40%
なぜ粗利益率を知っとくおくべきかと言うと、理由は2つ。
・銀行が気にするところ
粗利益率が高いと借入金の返済がしやすい、つまり利益がでやすい、ということ
上記の例で粗利益率が50%に上がったら500円。
極端に言うと税理士みたいな商売は仕入がないから100%、つまり1,000円になります。
よって粗利益率が高い、ということは少ない売上でも儲けることができる、つまり
借入金の返済原資が大した売上が上がらなくてもないしは減ってもそんなに影響しないことになります。
・税務署もよく見ています。
この粗利益率が5%上下に変動すると税務調査に来やすくなります。
これは売上を除外しているか、仕入を過大に計上しているか、在庫を過少計上しているか?このような場合に起こりやすいです。
税務署は過去3年間の推移を比較していますので、注意が必要です。
よくあるケースは売上の除外はするけれど、仕入は請求書があるからそのまま計上して粗利益率が5%以上減少して、おかしいな?と思い税務調査があります。
私も粗利益率が5%以上変動した場合には必ず原因を社長に確認しています。
2. 損益分岐点
固定費÷粗利益率
損益分岐点売上はその名のとおり収支がトントンになる売上のことです。
つまり赤字にならないための必要売上になります。
まずか予想固定費を計算してもらえれば赤字にならない売上がわかります。
この場合にも粗利益率が高いと固定費も少なくてすみます。
3. 安全余裕度
実際売上高-損益分岐点売上高
これは売上がここまで下がっても赤字にならない売上高を知っておくことができます。
4. 借入金の返済がある場合の損益分岐点
[固定費+支払利息+{借入金返済額/(1-税率)}]/粗利益率
例えば飲食店で内装工事に借入をしたとします。法人税の税率を40%とします。
利益60万円 返済額 60万円
確かに返済は可能です。ただし60万円の利益に対する税金が払えません。
よってこのままでは税金の滞納になってしまいます。
そこで60万円を1-税率(40%)で割り戻した100万円が利益として必要になります。そうすると返済60万円、納税40万円で資金が回ります。
▼今すぐこちらからお問い合わせください▼
LINEでお問い合わせ松岡靖浩税理士の
商業出版書籍 絶賛販売中!